「教養」と聞くと、少し難しく感じてしまうことはありませんか?
たくさんの本を読んでいて、歴史や文学にも詳しくて…。私はかつて、そんなイメージを持っていました。
でも、出口治明さんの著書『人生を面白くする 本物の教養』を読んで、その考え方がガラリと変わりました。
出口さんが言う「教養」とは、単なる知識の量ではありません。それは、「生きる力」であり、「グローバル化したビジネス社会を生き抜くための最強の武器」のこと。教養を身につけることは、人生をより深く、面白くする鍵なのだと教えてくれます。
教養の本質は、「自分の頭で考える」こと
教養の本質は、まさに「自分の頭で考える」ことにあります。
教養を身に付けるにはある程度の知識が必要ですが、知識はあくまでも道具であり、手段にすぎません。「知っている」だけでは不十分で、知識を素材として「自分の頭で考える」ことが教養なのです。
「自分の頭で考える」際のバロメーターとして、「腑に落ちる」という感覚が挙げられます。誰かの話を聞いて、本を読んで、自分の頭で考えた上で理屈ではなく腹の底から「本当にその通りだ」と思えるかどうか。私もこの感覚は大切にしていて、本当に腹落ちしたことは確実に自分の力になっていると感じています。
物事を「国語ではなく算数で考える」
物事を考えるときには、「国語(定性的)ではなく算数(定量的)で」考えるという視点が重要です。
これはつまり、理屈や感情だけでなく、「数字」で考えるということです。
定性的:主観的な判断や観察に基づく情報を扱う
定量的:数値で表現できる情報を扱う(客観的な測定が可能)
定性的な視点だけでは、筋道が成り立ちさえすればどんな理屈でも言えてしまう一面があります。そこに定量的な視点を加えることで、物事をより正確に把握することができるのです。
この本では、例として「税金の無駄遣いをなくせば消費税を上げなくてもすむ」という意見を取り上げています。理屈として成り立っているこの意見を数字を用いて簡単に計算することで、現実的に実現可能かどうか考えていく過程にはとても興味深いものがありました。
自分に都合が良くて耳障りの良い意見は、深く考えずに受け入れたくなる気持ちも分かります。しかし、一歩踏み込んで数字で考えることが教養人になるための第一歩なのではないでしょうか。声が大きい方に賛同するだけの人に、自分軸や教養を感じる人はいないと思います。
余談ですが、私は「国語ではなく算数で考える」視点を意識するようになってから、選挙ポスターを見るのが楽しくなりました。
本の内容を「血肉化」する読書術
知識を蓄えるためには読書も有効ですが、ただ文章を目で追うだけでは不十分です。本の内容を「血肉化」するためには、読み方に工夫が必要です。
読み返す
「早く読み終えたい!」とスピード重視で本を読んでしまうと、読み終わった直後なのに「何が書いてあったか思い出せない」なんてこと、ありませんか?
本の内容を血肉化するためには、「分からないところが出てきたら、腑に落ちるまで何度も同じ部分を読み返す」ことが近道だそうです。
スピードを気にすることをやめてじっくり読み返すことを意識してからは、本から得られる情報が多くなったように感じています。
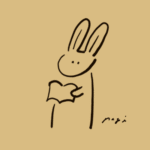
いつの間にか「読み終えること」がゴールになってたりしない?
速読は百害あって一利なし?
効率的な読書術として紹介されることも多い速読ですが、著者は「百害あって一利なし」と言っています。急ごしらえの読書では内容が血肉化されず、結局読んだ意味がありません。
本を読むスピードを上げる最も効率的な方法は、実は「本をたくさん読むこと」だそうです。人名や用語などの知識の蓄積があるほど、つまづかずに読み進めることができます。
本を読むのにかかる時間は、その人の知識量で決まってくるものであり、単純に目で文字を追う速度とは違うのです。
(出口治明さん「人生を面白くする 本物の教養」,幻冬舎,2015年9月,105ページ)
教養の入門書
以前は、教養=知識の量だと思っていました。しかしこの本を読んで、「知っている」だけでは不十分で、その知識を基に「自分の頭で考える」ことが何よりも重要だということに気が付かされました。
教養という言葉にただ無条件に惹かれていた私ですが、教養の本質を知って、以前より知ることの楽しさ、学ぶことの喜びを感じられるようになりました。
また、著者の豊富な話題はとても面白く、私も身の回りの問題(例えば職場の会議室の適正数など)について考えるきっかけとなりました。
もしあなたが「教養」という言葉に少しでも興味があるなら、まずは【人生を面白くする 本物の教養】を手に取ってみてください。きっと、新しくて楽しい世界が広がりますよ。
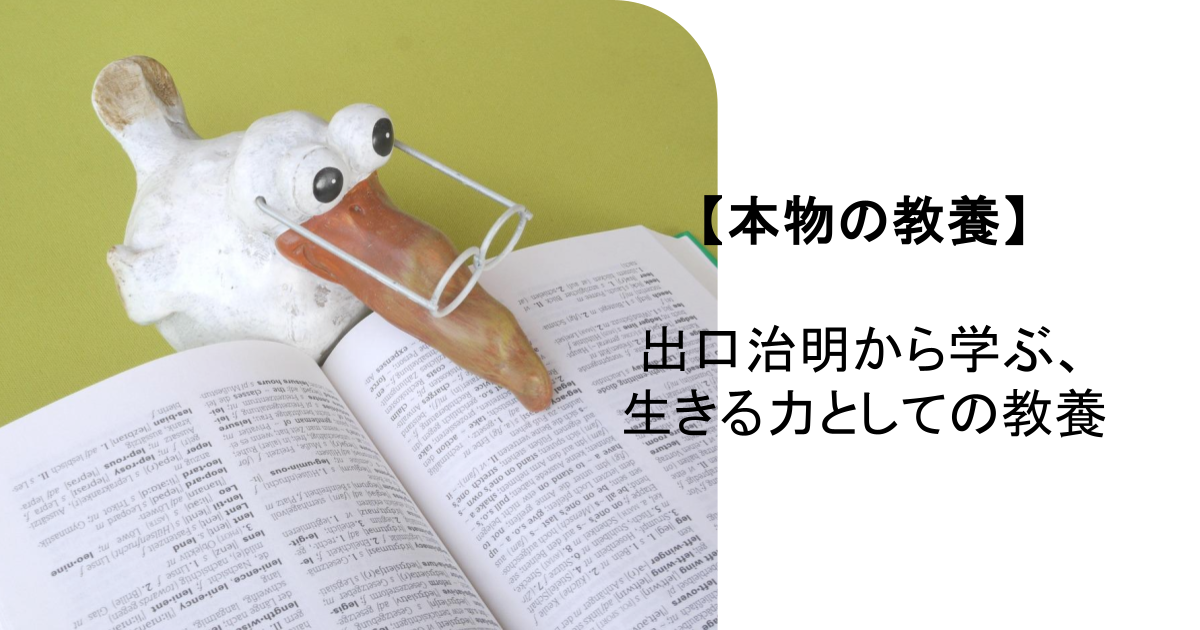

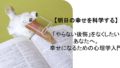
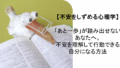
コメント