見波利幸さんの著書『平気で人をいじめる大人たち』は、職場の人間関係に悩むすべての人に読んでほしい一冊です。
いじめられていて辛い思いをしている方、いじめがある職場で働いている方、そして、もしかしたらいじめてしまっているかもしれないと自問する方に。
この本は、大人としてふさわしい、より賢明な対抗策を私たちに提示してくれます。
「いじめをする人」は、なぜ平気でいじめられるのか?
いじめをする人たちは、多くの場合「自分は正しいことをしている」と思い込んでいます。「これは教育だ」「指導の一環だ」と、自分を正当化することで、いじめの事実から目を背けているのです。
自分が正義だと信じているからこそ、平気で人の気持ちを踏みにじることができる。この本は、そんな彼らを3つのタイプに分けて分析しています。
- 感情型: 自分の好き嫌いで物事を判断し、感情のままに行動してしまうタイプです。例えば、この本の事例で取り上げられた女性は、嫉妬という感情がいじめの根源でした。
- 自己愛型: 人を自分より上か下かで判断し、常に自分が優位に立ち、賞賛されることを望みます。自己の承認欲求を満たすために、他人を攻撃します。
- 他者利用型: 他人を自分の目的のために利用する道具としか見ていません。周囲の人間がどうなろうと一切気にせず、目的のためなら手段を選びません。
あの人はこのタイプかもしれない…と頭に浮かぶ「あの人」がいた場合は、ぜひ実際に本を手に取ってみてください。
本を読むことで「あの人」への理解がより深まり、解決策が得られることを願っています。
タイプ別の対応策と、あなたにできること
この本では、それぞれのタイプへの対応方法が具体的に紹介されています。
- 感情型の相手には、自己防衛が不可欠です。「つまらないことで意地悪をする人がいる」と割り切り、距離を保ちつつ、相手への配慮を見せることで嫉妬の感情を和らげることができます。
- 自己愛型の相手には、アサーティブなコミュニケーションが有効です。相手の気持ちを尊重しながらも、自分の意見を素直に伝えることで、相手の攻撃性を抑える効果が期待できます。
- 他者利用型の相手に対しては、根本的な解決策はほとんどありません。しかし、相手を敬う気持ちを見せることで、攻撃を収められる可能性もあります。人は基本的に、自分を尊敬している人を否定することは難しいものです。
これらの対応策は、いじめの状況を悪化させないための知恵です。
しかし、最も大切なのは、「自分が加害者にならない」という強い覚悟を一人ひとりが持つことです。自分と違う考え方や価値観を持つ人間を排除しようとするのは、人間の弱い部分。だからこそ、常に他人の気持ちを大切にすることを意識し、自分自身への戒めとする必要があります。
最終的な解決策としての「傾聴」
いじめの問題を考える上で、覚えておいてほしいのが「傾聴」というスキルです。この本では、いじめの解決策の一つとして、この「傾聴」の重要性を説いています。
傾聴とは、単に相手の話を聞くことではありません。相手の気持ちに寄り添い、「あなたはこんな気持ちになっているのですね」と共感し、その感情を受け止めることです。
人が変わるために必要なことはたった一つ。
誰かがその人の気持ちをきちんと感じ取り、相手に伝えることです。
これだけで人は生きていくことができるのです。
傾聴のスキルを身につけることで、私たちは次のことができるようになります。
- いじめる側の「孤独」を解きほぐす: 傾聴によって、いじめをする人の心の奥底にある不安や孤独に気づくことができます。もちろん、彼らの行動を許容するわけではありませんが、対話によって、いじめの連鎖を断ち切るきっかけを作れるかもしれません。
- いじめの被害者に寄り添う: いじめを受けている人は、誰にも分かってもらえない孤独感に苦しんでいます。あなたが「傾聴」することで、その人の心の支えとなり、孤独な戦いに終止符を打つことができます。
- 傍観者から脱却する: いじめを黙認してしまう背景には、「何を言っても無駄だ」という諦めや、同調圧力への恐怖があります。しかし、傾聴を通じて相手の感情を理解できるようになると、その「空気」に流されず、「これはおかしい」と声を上げる勇気が持てるようになります。
あなたの勇気が、誰かの未来を変える
私自身、前職で精神的にダメージを受けていた同僚を助けたいと悩んでいた時に、この本と出会いました。
直接的な解決ができず、「大丈夫?」と声をかけることしかできなかった私に、その同僚は「気にかけてくれている人がいるだけで救われる」と笑顔を見せてくれました。
この出来事とこの本が、私に傾聴スキルを本気で学ぼうと決意させてくれたのです。
「自分はカウンセラーではないから…」と諦める必要はありません。あなたの存在と、ほんの少しの勇気が、誰かの生きていく力になる。この本から学び、あなたも「誰かの生きていく力」になってみませんか?
自己紹介と、ブログを始めた動機や私が思う本の魅力について書いた記事です↓
こちらもぜひのぞいてみてくださると嬉しいです!

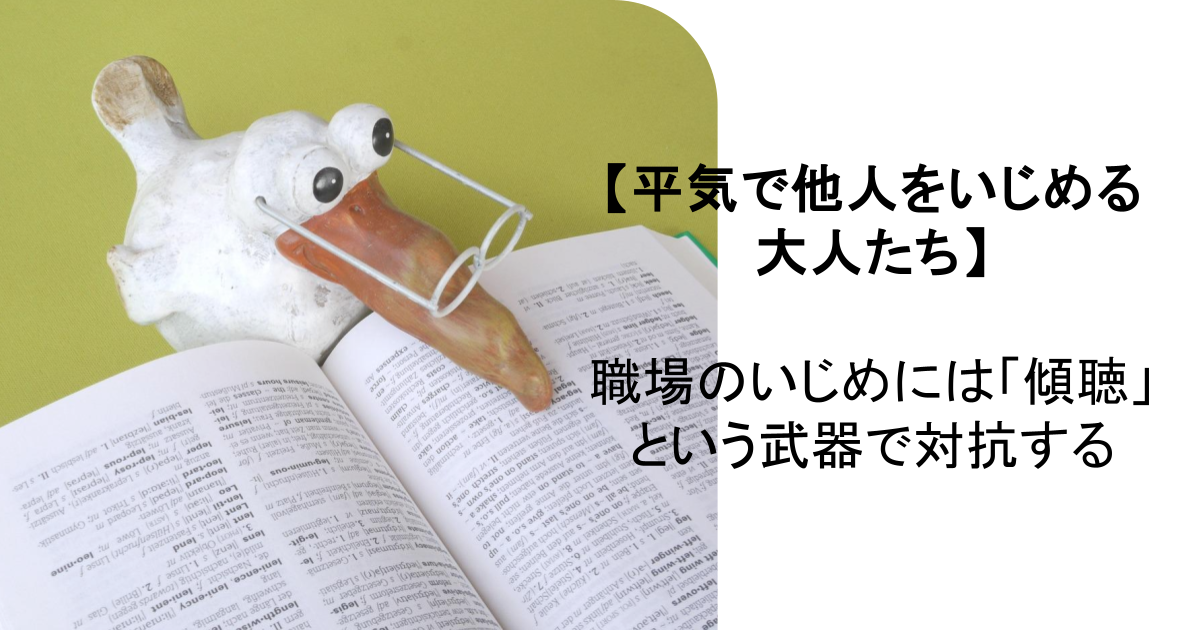

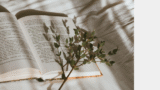
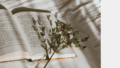
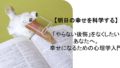
コメント