「最近、なんだか考え方が凝り固まっているな…」と感じることはありませんか?
今回は、そんなあなたのものの見方をアップデートしてくれる一冊、戸田智弘さんの『ものの見方が変わる 座右の寓話』をご紹介します。
新鮮な気づきが欲しい方はもちろん、日々のスピーチやプレゼンのネタを探している方にも、きっと役立つはずです。
寓話の力
「寓話」とは、教訓や風刺が込められた短い物語のこと。動物や架空の人物が登場し、人生の真理を間接的に伝えてくれます。
直接的な説教では心に響かないことでも、物語の登場人物に感情移入することで、楽しみながら自然と教訓を学べるのが寓話の魅力です。
この本には77の寓話が収録されていますが、今回はその中から特に心に響いた3つの寓話をご紹介します。
事実は一つ、解釈は人それぞれ:双子の運命
過酷な環境で育った双子の話です。30代になったとき、一方は父親と同じく薬物中毒に、もう一方は幸せな家庭を築いていました。
「なぜこうなったのか?」という問いに対し、二人は口を揃えてこう答えました。
「あんな家庭に育った私に、これ以外の何ができるというんだ!」
同じ事実を経験しても、その解釈は全く異なります。
自分の身に起こる事実は選べませんが、その事実にどう向き合い、どう行動するかは、私たち自身が選ぶことができます。人生を変える鍵は、この「解釈」にあると気づかされました。
競争するのは「善い人」?それとも「悪者」?:悪者ぞろいの家
この寓話では、悪者ばかりの七人家族と、善い人ばかりの三人家族が登場します。面白いのは、悪者家族は仲睦まじく、善い人家族は喧嘩が絶えないという点です。
なぜでしょう?
悪者家族の家では、茶碗が割れると「私の不注意だった」と、われ先に悪者になる競争をします。
一方、善い人家族の家では「私は知らない、あなたが悪い」と、お互いが善い人になろうと罪をなすり付け合うのです。
「善い人」になろうとするあまり、他者を責めてしまう(他責思考)私たちの姿を鋭く風刺しています。
自分は悪くない、正しい、と主張する前に一度立ち止まって考えてみませんか?
知らず知らずのうちに、あなたも誰かと「善い人」の座を奪い合っていませんか?
「なるようになる」の真意とは?:一休和尚の遺言
「一大事が生じたら開けるように」と、一休和尚が弟子に残した箱。
長い年月を経て箱を開けると、中には「なるようになる。心配するな」と書かれた紙が入っていました。
これは単なる楽観的なメッセージではない、という著者の解釈にハッとさせられます。
「なすべきことをなせ」というメッセージが前提として隠れているのではないか、と。
やるべきことをやり切ったからこそ、あとは「なるようになる」と腹をくくれる。結果をただ待つのではなく、まず自分にできることを全力でやる。このシンプルな教訓に、背中を押される思いがしました。
さあ、寓話で心を耕そう
子どもの頃は、良くも悪くも周りからの影響を受けながら、たくさんの価値観を学びます。
しかし大人になるにつれて、自分の考え方や価値観が確立され、新しい視点を取り入れる機会が減りがちです。ともすれば、自分と異なる考え方の人を否定してしまうなんてことも…。
国も時代も異なる多様な寓話に触れることで、凝り固まった思考がほぐれたり、ネガティブな思い込みに気づけたりするかもしれません。
『ものの見方が変わる 座右の寓話』は、あなたの心を豊かにし、穏やかな日々を送るためのヒントを与えてくれるはずです。
大人のあなたも、寓話の世界で楽しく視野を広げてみませんか?
自己紹介と、ブログを始めた動機や私が思う本の魅力について書いた記事です↓
こちらもぜひのぞいてみてくださると嬉しいです!

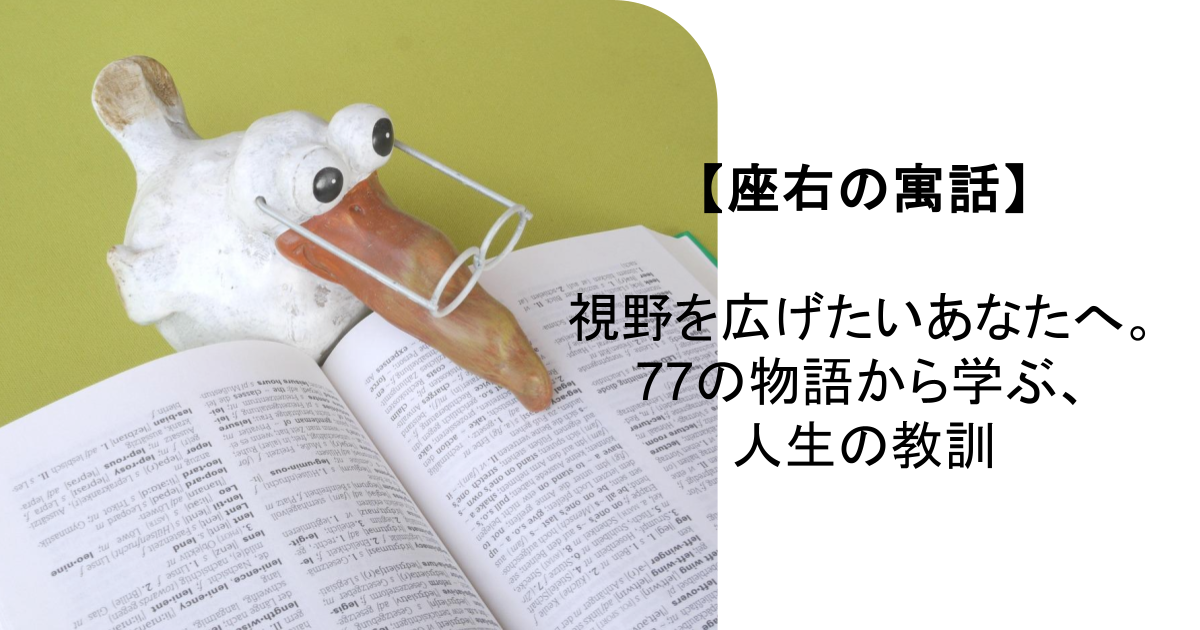

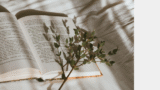
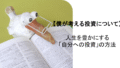
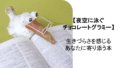
コメント